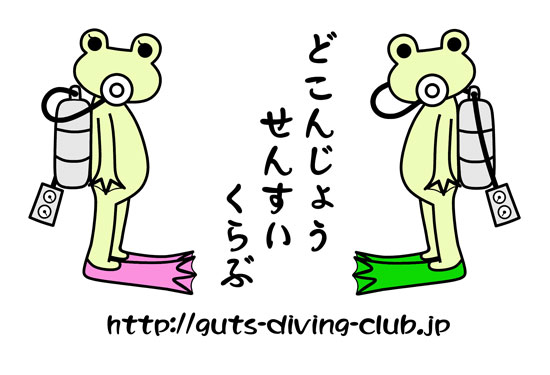ギャラリー蛇足 企画展
「わたしのなかのモットー展vol.2」
終了しました。
ギャラリーへお越しいただいた方々、
ありがとうございました!
在廊と搬出のタイミングでまたまた潜ってきました!
9月中ばになってもなかなか暑さが和らぎません。
さすがに35℃を超える猛暑日は少なくなりましたが、
いまだに真夏日の連続です。
しかし、空を見上げると、
ちょっとだけ秋の気配も感じられます。
秋の空と夏の空のブレンドといった感じでしょうか。
=======================================
画像をクリックすると同ウインドウで拡大表示されます。
「×」ボタンで戻ってください。
=======================================
8月の海がとても冷たかったので、
用心してロクハンで潜りましたが、
深場でも水温が27〜28℃あり、
危うく水中で熱中症になりそうでした。
ウミヒルモ

いまだに花をみることができていません。
時季的なものなのか、高水温の問題なのか、
全体的に萎れた感じになっていました。
魚たちにほじくり返されて露出していた地下茎の先に
生長点のようなものがあります。
また、地下茎から葉が分岐している部分に根が生えているのがわかります。
ニセゴイシウツボyg

わりと臆病で、すぐに奥に引っ込んでしまいます。
名前に”ニセ”がつくということは、
当然、本家のゴイシウツボがいるはずなのですが、
なぜか存在しません。
というか、ゴイシウツボは消えてしまいました。
かつて、ニセゴイシウツボの成魚がゴイシウツボ、
幼魚がニセゴイシウツボと呼ばれており、
別種扱いだったそうです。
後に両者が同種ということがわかり、名前を統一する際に、
先に学名が確定していた幼魚の方の和名が残ったとのこと。
なんとも数奇な命名の歴史を辿ったのですね。
学術上の都合で名前をあてがわれてしまって
かわいそうな気もしますが、
本人たちにとってはどうでもよいことなのでしょう。
ハタタテダイyg

いつ見てもムレハタタテダイと区別できません。
ホシハゼyg

カスリハゼのちびっこがたくさんいるとの情報だったのですが、
ホシハゼのちびっこしか見つけられませんでした。
ですが、可愛いに違いはありません。
ミナミハナダイ

以前から見かけてはいたのですが、
なかなか写真に収めきれずにいました。

ベストショットとはいきませんが、
なんとか写すことができました。
ソリハシコモンエビ属の一種
(通称クリアクリーナーシュリンプ)

ソリハシコモンエビ属の中では
最も目にする機会は多いと思うのですが、
なぜかまだ標準和名がついていません。
額角が先端から赤・白・赤と続きます。
ベンテンコモンエビ

同属他種よりも赤い斑紋が密になっていて、
額角が先端から白・赤・白と続きます。

比較的南方系のハゼだったと思うのですが、
やはり温暖化の影響でしょうか?
メガネスズメダイyg

クロメガネスズメダイの幼魚と混同していました。
尾鰭の付け根にくっきりと白帯があることが
メガネススメダイの特徴だそうです。

ミヤコキセンスズメダイの方は、
エラの部分の黄色が濃くなっていることで見分けられます。
モンツキベラyg

8月に見た時はイソバナ背景で撮影しました。
今回はオレンジのトサカ背景です。
ベニヒレイトヒキベラ

3匹ほど集まって泳いでいました。
どうもうまく撮影できません。
ミナミギンポ

背鰭が赤くなり、青いラインが鮮やかになって、
婚姻色の様相が現れています。
トカラベラyg

岩陰から出てきたり引っ込んだりしながら
マユハキモを啄んでいました。
ベンケイハゼ

ペアでいましたが、
1匹奥に引っ込んでしまいました。
ソメワケヤッコ

黄色の魚と青色の魚を前後半分ずつ
切って貼ってくっつけてつくりました・・・って
まさにそんな感じの不思議な配色です。
ミノカサゴyg

瞳の中にまるで稲妻が走ったような模様が浮き出ています。
クロホシイシモチ

おしりから白い紐状のものをたなびかせているものがいました。
詳しくはわからなかったのですが、
体調不良(下痢か栄養不良?)によるもののようです。
ハタンポ幼魚の群れ

ハタンポにしては珍しく
明るい場所に出てきて群れていました。
子ども達は陽の当たるところが好きなのかな?